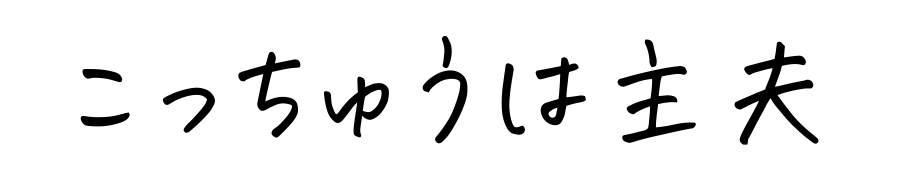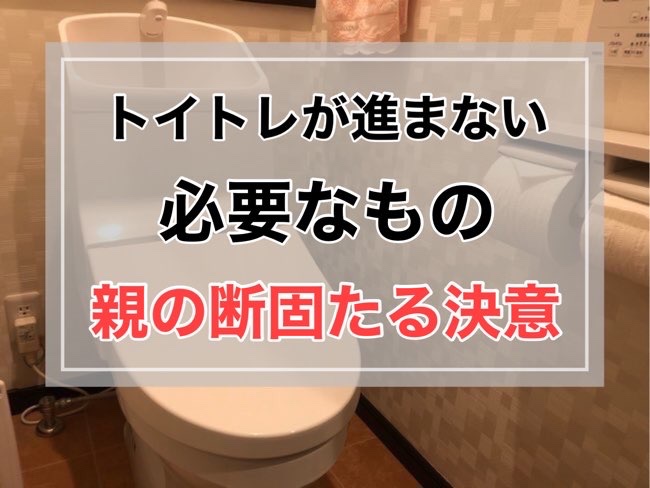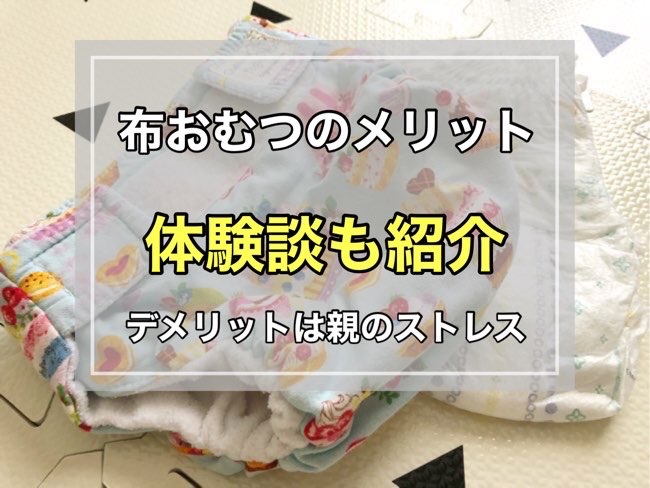こんにちは!主夫2年目のこっちゅう【プロフィールはこちら】です。
子どもたちのかわいいオムツ姿の卒業を目指し、トイレで排泄できるようにするための「トイレトレーニング」。
景気よく子どもの走りまわる姿を見ると「そろそろ始めるべきなのでは?」「どうやって進めたらいいの?」と悩む親も多いのではと思います。

もちろんわたしも悩める親の1人です。
というわけで今回は「トイレトレーニングのやり方」についてまとめてみました。
広告
トイトレとは?
まず、トイトレについて簡単に説明しますね。
トイトレとは、トイレトレーニングの略語です。
いままでおむつでおしっこやうんちをしていた赤ちゃんが大人と同じように「トイレ」という決められた場所で排泄ができるようトレーニングをすることです。

子どもがトレーニングをはじめる前は常におむつを使っていたため、「おしっこをしたい」「うんちが出そう」という感覚を完全に無視して排泄していたという根本のところから変えていなければいけません。
また、トイレという存在が何なのかをそもそも知らないため、そのあたりも含め教えてあげる必要もありますね。

子どもの成長に合わせてはじめましょう!
トイトレが進まない原因 → 親の断固たる決意がないから!
まず、トイトレをはじめるにあたって大切なことがあります。
それは、「親がトイレトレーニングを意地でやめない」という断固たる決意です。
子どもがトイレトレーニングをはじめるタイミングになっていても、結局のところ親がトイレトレーニングをはじめようとしなければトイレトレーニングははじまりません。
また、トイトレがうまくいかない・進まないと思ってイライラ。
そんな親の都合で挫折するような覚悟では、トイトレは進みません。
そのため、「トイレトレーニングをはじめるぞ!」「絶対にトイトレを完了させるぞ!」という覚悟がトイトレが進んでいく唯一の方法です。

ただ親の脳内がパンクしないように!
トイトレのやり方
では、トイレトレーニングはいつからはじめたらいいんでしょうか?
トイレトレーニングをはじめるタイミングとなるポイントが個人的には4つあります。
- オシッコの間隔が2時間以上空く
- ひとり歩きが上手にできる
- 自分の意思がしっかりと伝えられる
- 始める時期は夏〜秋の季節がオススメ!

ひとつずつ説明します!
【1】オシッコの間隔が2時間以上空く
まず、子どものオシッコをする間隔が2時間くらい空くというのがポイント。
オシッコをする間隔が2時間くらい空くようになるということは、オシッコを膀胱にためられるようになったというサインになるみたいです。

布おむつで子どもを育てていると、このへんの感覚は自然と身についてしまう気がしますね。

排尿の間隔をチェックしておく必要があるんだね
ちなみに「布おむつと紙おむつどっちがいいの?」と気になる方はコチラの記事を参考にしてみてくださいね。
【2】ひとり歩きが上手にできる
そして、子どものひとり歩きが上手にできるようになるのがもうひとつのポイントです。

運動能力の発達は子どもの脳が発達している証拠にもなりますし、ひとり歩きが上手にできるというのは「子ども自身が感じたことや思ったことを行動に移すことができる」ということですよね。
なので、この原理でいくと子どもは「オシッコが膀胱にたまっている」っていうことも容易に把握できるようになっているそうです。
【3】自分の意思がしっかりと伝えられる
トイレトレーニングに限らず、育児でもっとも大切なのはやはり「子どもとのコミュニケーション」ですよね。
そのため、子どもが自分の意思をある程度は伝えられないとトイレトレーニングはなかなか難しいように思えます。
なので、子どもが「ママ 歌って」や「パパ 読んで」、「ちっち 出た」など、2語文を話すようになるとある程度コミュニケーションがとれるので、トイレトレーニングをはじめる一つの判断基準になりますね。

子どもと一緒に絵本を読んでいるとはやい気がします。
【4】始める時期は夏〜秋の季節がオススメ!【洗濯が楽】
ちなみに、夏〜秋の季節にトイレトレーニングをはじめると、いろいろとラクになります。

だって、おもらしで汚れたパンツを洗ってもすぐに乾くんですよ。
さらには、おむつ交換時に毎回パンツ1枚でウロウロしていても風邪をひきにくいですよね。
なので、夏はトイレトレーニングをするには最高の季節なのです!!。
トイトレをはじめるために揃えるもの
トイレトレーニングをはじめる前に、実際にわたしが準備したアイテムを紹介します。
ということで、準備したアイテムはたったの3つです。
- 補助便座
- 踏み台
- トイレトレーニングパンツ
【1】補助便座
まずは、やっぱり補助便座が必要ですよね。

この補助便座をトイレに常に置いておき、子どもがトイレに突入する際に補助便座を設置するといういたってシンプルな作戦。
ちなみに、子ども的にはおまるの方がトイレトレーニングに取り組みやすいということもあるかもしれません。また、和式トイレ対策にも「おまる」はオススメですよね。
しかし、個人的には和式トイレもあまり見かけなくなっているのもありますし、おまるの後には補助便座を使ってのトイレトレーニングがあります。
結局のところ、2度デマになるような気がしたので「おまる」は必要ないトレーニングと考えました。

親の独断と偏見の決断です!
【2】補助台
つぎに子どもが自分で上がれるように補助台です。

補助便座に階段がついているようなタイプもありますが、なんか親しみがわかないのでやめました。スペースも結構とりそうですもんね。
ちなみに補助便座と補助台をセパレートしていることで、補助台は洗面台やキッチンなのいろいろシーンでも活躍できるのもいいですよね。

トイレの景観も崩してしまう気がして我が家ではNGで
【3】トイレトレーニングパンツ
そして、おむつの代わりとなるトイレトレーニングパンツです。

トイレトレーニングパンツのポイントとしては、親が子どもに履いてもらいたいデザインにするということですかね。
このトレーニングパンツを履いている子どもを見ることが癒やしとなり、トイレトレーニングのしんどさを乗り切ることができると信じています。

わたしの場合、トレーニングパンツ5枚でのローテーション
トイトレの進め方
さて、具体的なトイレトレーニングの方法についてですが、ただおむつをやめて布パンツを履かせるだけなのです。
ざっとトイレトレーニングの流れはまとめてみました。
こんな感じの流れですよね。
- 布パンツを履かせる。
- 1時間に1回程度はトイレに誘ってみる。
- トイレにいくことを嫌がればトイレには行かない。
- トイレが上手にできた場合は、子どもを褒めたたえる。
- トイレがうまくいかなかった場合は、ドンマイ精神で肩をぽんっとたたく
- 布おむつに漏らしてしまう。
- おしっこを拭いて濡れたパンツを洗い、新しい布パンツを履かせる。
この流れをひたすら繰り返して、「おしっこはトイレでする」ということを子どもにわかってもらう必要があります。
基本的には「漏らして覚える」という考え方がベースになりますね。
そのため、布おむつのほうが紙おむつより「おむつ卒業がはやくなる」っていうのもうなずけるってもんです。

とってもシンプルな方法ですが、親の根気が1番大切です。
まとめ
さて、今回は「トイレトレーニングのやり方」についてお話をしました。
正直3日目くらいで「まだ早かったかも」とあきらめそうになりますが、絶対にあきらめてはダメですよ!
約30日もあれば、子どもは「おしっこはトイレでする」ということを必ず覚えてくれます。
心が折れそうになっても「オムツが節約できてラッキー」という考えに切り替え、ひたすら前向きに取り組めばいいのです。
ちなみに絵本などを使って日常生活からい「トイレに行く」という行為を丁寧に教えてあげるとスムーズに進んでいくかもしれませんね。

とにかく「おむつ卒業」のカギは間違いなく親の根気ですよ!!
広告

せっかくだから「子育てのカテゴリ」も見てよね〜